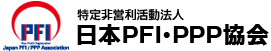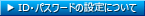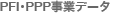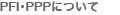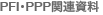PFI・PPP関連ニュース
▽2024.4.26
自民国立劇場再整備PT/整備の在り方、骨太方針に反映へ/コストアップへの対応必要
自民党の文化立国調査会のプロジェクトチーム(PT)は、国立劇場の建て替え整備に関する関係団体からのヒアリングを24日までに終えた。同日の会合では、人件費をはじめとする建設コストの上昇が著しい状況とともに、立地などの関係から「挑戦しにくい事業だった」などの説明があったという。今後は同調査会で、2025年度の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)に整備の在り方を反映させる方向で議論を続けていく。国立劇場を巡っては、再公告したPFI法に基づく一般競争入札(WTO対象)が落札に至らず、自民党は同調査会に国立劇場再整備・文化投資拡充PT(座長・遠藤利明衆院議員)を設け、伝統芸能を伝承・創造する中核拠点として整備するための対応を検討している。同日の会合では、参加議員から民間の提案やノウハウを生かすPFI方式に期待する意見が出る一方で、同方式にこだわらずに「国が責任を持って整備する」ことを求める意見も出た。
情報元:建設工業新聞
関東整備局/24年度1回目官民連携基盤整備推進費/長野県千曲市IC周辺整備を支援
関東地方整備局は24日、「官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業(官民連携基盤整備推進調査費)」の2024年度第1回配分を公表した。全国9市町のうち関東管内では長野県千曲市を採択。同市が「(仮称)屋代スマートIC」の周辺で計画している交通拠点整備を通じた地域活性化を支援する。補助率は2分の1。同市が実施する基礎調査や概略設計、PPP/PFI導入可能性調査の事業費1600万円の半分を国が補助する。本年度は交通拠点整備に関する基礎調査や基本計画策定、概略設計、PPP/PFI導入可能性調査を実施する予定だ。
情報元:建設工業新聞
国交省/官民連携基盤整備推進調査費、静岡県富士市と津市に配分
国土交通省が進める「官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業(官民連携基盤整備推進調査費)」の2024年度第1回配分で、中部地方整備局管内から静岡県富士市の「田子の浦港の新たなにぎわい創出に向けた基盤整備検討調査」と、津市の「津駅周辺エリア再整備による地域活性化のための基盤整備検討調査」が選ばれた。いずれも調査費の半額を助成する。両市は今後、事業化に向けた基礎調査やPPP/PFI導入可能性調査を行う。情報元:建設工業新聞
国交省/官民連携による地域活性化基盤整備推進支援事業/四国管内から2事業選出
国土交通省の「官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業(官民連携基盤整備推進調査費)」の2024年度第1回配分先として、四国地方整備局管内では香川県小豆島町の「瀬戸内海の離島観光拠点の再生に係る基盤整備検討調査」と松山市の「松山駅周辺地区における広域交流拠点整備のための基盤整備検討調査」が選ばれた。民間の設備投資などと一体的に計画されるインフラ整備の具体化に向けた調査を支援する。事業費は小豆島町が4070万円、松山市は3180万円。それぞれ半額を補助する。
情報元:建設工業新聞
関東整備局/24年度1回目官民連携基盤整備推進費/長野県千曲市IC周辺整備を支援
関東地方整備局は24日、「官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業(官民連携基盤整備推進調査費)」の2024年度第1回配分を公表した。全国9市町のうち関東管内では長野県千曲市を採択。同市が「(仮称)屋代スマートIC」の周辺で計画している交通拠点整備を通じた地域活性化を支援する。補助率は2分の1。同市が実施する基礎調査や概略設計、PPP/PFI導入可能性調査の事業費1600万円の半分を国が補助する。本年度は交通拠点整備に関する基礎調査や基本計画策定、概略設計、PPP/PFI導入可能性調査を実施する予定だ。
情報元:建設工業新聞
▽2024.4.25
ウオーターPPP推進などテーマに/FJISSと国交省、6月にも意見交換
持続可能な社会のための日本下水道産業連合会(FJISS、野村喜一会長)は、第5回となる国土交通省との意見交換会のテーマを固めた。ウオーターPPPの推進と業界の働き方改革、人材確保を中心に提言内容をまとめ、意見を交わす考えだ。18日に開いた第20回理事会で審議した。意見交換会は6月から7月にかけて開催する方向で調整を進めており、これに合わせて詳細な内容を詰めていく。
この日の理事会では、第5回(2024年度)定時社員総会を6月13日に招集することを承認した。ホテルグランドアーク半蔵門を会場に午後3時30分に開会する。
情報元:建設通信新聞
▽2024.4.24
品川区、公共施設等総合計画を改定/施設類型ごとに方向性/更新・改修経費は年間151億
東京都品川区は、「公共施設等総合計画」を改定した。AI(人工知能)やデジタル技術の進展など社会経済状況の変化を踏まえ、2017年に策定した同計画を見直した。区内の335施設を対象に施設分類ごとに「個別施設計画」を示し、効果的に維持・更新を実施する。必要経費は、今後30年間で1年当たり平均151億8000万円を見込む。民間活力の活用を検討するため、PPP/PFI手法導入優先的検討規程を定め、計画に盛り込んだ。計画期間は24年度から33年度の10年間。公共施設の現状としては、大規模改修の目安である築30年以上の施設が半分以上を占め、老朽化が進行している。特に築40-50年以上の施設の割合が増加しており、区有施設は前計画よりも全般的に老朽化が進行している。
情報元:建設通信新聞
▽2024.4.22
国交省が5月31日まで募集/官民連携基盤整備調査費
国土交通省は、民間と自治体が連携して取り組むインフラ整備の事業化検討を支援する官民連携基盤整備推進調査費について、2024年度第2回募集を5月31日まで受け付けている。7月下旬以降に配分する。国交省所管の道路、海岸、河川、港湾、都市公園、空港などの公共土木施設整備の事業化に向けた検討経費を支援する。具体的には基礎データ収集、需要予測、概略設計など事業化に必要な調査やPPP/PFI導入可能性検討調査の費用の2分の1を補助する。
情報元:建設通信新聞
▽2024.4.18
法務省有識者会議/国際法務総合センターの事業評価まとめる/民間委託の継続を提言
法務省の有識者会議は、同省がPFI方式で運営する「国際法務総合センター」(東京都昭島市)の事業評価をまとめた。民間のノウハウを生かし、業務の効率化を実現できていると評価。事業期間が終了する2026年度以降も、民間委託を継続すべきと提言した。法務省は評価結果を踏まえ、次期事業の具体的な内容を詰める。次期事業のスキームは、現行と同様に委託対象の業務を広く包括的に委託する方式を提言した。民間事業者の参入ハードルは高くなるものの、一体運営による行政の効率化の実現が期待できるとした。
情報元:建設工業新聞
経産省/市場形成力が高い10社公表/建設産業関連インフロニアHDなど
経済産業省は17日、ルール形成による市場創出に取り組む企業10社を公表した。市場形成力が高い企業として、建設産業関連ではインフロニア・ホールディングス、コマツ、積水化学工業、ダイキン工業が選ばれた。経産省は規制や標準、業界基準などのルール形成に企業が自ら取り組み新たな市場を創出する力を「市場形成力」と定義し、それを可視化する「市場形成力指標」を2021年に開発。22年には改良版の指標を公表した。
公表企業の取り組み事例を見ると、インフロニア・ホールディングスは、ホールディングス発足前の前田建設工業の取り組みとして、PFI法の公共施設等運営権の導入に向けた協議に参加し、ルールが未整備だったコンセッション事業の法制度化により国内市場を創出した。
情報元:建設通信新聞
▽2024.4.15
PPP/PFIプラットフォーム/4地域と協定
内閣府と国土交通省は、PPP/PFI地域プラットフォーム協定制度の第6次募集で、新たに四つの地域プラットフォームを協定先に選定した。協定先の累計は36地域となった。新たな協定先と代表者は次のとおり。
▽宇都宮PPP/PFI地域プラットフォーム(宇都宮市)▽にいがたPPP/PFI研究フォーラム(新潟県、第四北越銀行)▽岡崎市SDGs公民連携プラットフォーム(愛知県岡崎市)▽鹿児島県PPP/PFI地域プラットフォーム(鹿児島県)。
情報元:建設通信新聞
国交省/24年度は57団体採択/3D都市モデル整備・活用
国土交通省は、3次元都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を進めるプロジェクト「PLATEAU(プラトー)」の一環で、自治体の3次元都市モデル整備・活用を支援する2024年度の「都市空間情報デジタル基盤構築支援事業」に57団体の事業を採択した。これにより、3次元都市モデルを整備・活用する都市は24年度末に約250カ所に広がる。採択事業の分野別の内訳は「防災・防犯」が23団体、「環境・エネルギー」が3団体、「地域活性化・観光・コンテンツ」が2団体、「都市計画・まちづくり」が27団体、「その他」が2団体。
情報元:建設通信新聞
和歌山市/北部新浄水場を整備/新水道事業ビジョン今後10年の施策示す
和歌山市は、「和歌山市水道ビジョン2024」を策定した。水道施設の強靱化などを目的に今後10年間に進める施策をまとめ、紀の川に架かる送水管の複線化と北部新浄水場の整備を明記したほか、老朽化する水道施設にアセットマネジメントの考え方を取り入れ適切な維持管理を進める。事業推進に当たり、近隣水道事業者との広域連携やPPP/PFIなどの官民連携にも取り組む。同ビジョンは、2021年に起こった紀の川の六十谷水管橋崩落を受けて検討を進めてきた。計画対象期間は24年度から33年度の10年間。
情報元:建設通信新聞
▽2024.4.11
国交省/民間提案型 官民連携モデリング事業/ニーズ・シーズ提案に86件
国土交通省は8日、先導的な官民連携の自治体に広げる「民間提案型官民連携モデリング事業」の一環として、PPP/PFIのモデル形成に向けたシーズとニーズの公募結果を公表した。民間事業者のシーズ提案は77件、自治体のニーズ提案は9件寄せられた。22、23の両日に民間事業者がシーズ提案の内容を説明するアピールタイムをオンラインで開く。シーズ提案の内訳は、「インフラの維持管理・修繕等」が40件、「災害対策・復旧を見据えたインフラ整備・維持管理」が27件、「無電柱化」が1件、「スモールコンセッション」が11件、「グリーンチャレンジ」が7件、「その他」が4件だった(重複含む)。
ニーズ提案は「インフラの維持管理・修繕等」が4件、「災害対策・復旧を見据えたインフラ整備・維持管理」が1件、「スモールコンセッション」「グリーンチャレンジ」がともに2件だった。
アピールタイムで官民マッチングを促す。優れたシーズ提案は国からの調査委託によりニーズ提案者などの自治体でケーススタディを実施する。モデル事業となる新たな官民連携手法を構築し、取り組みの横展開を目指す。調査委託の公募は5月下旬から始め、7月上旬に15件程度を決める。
情報元:建設通信新聞
▽2024.4.10
国交省/24年度PPP・PFI支援/先導的官民連携29件
国土交通省は、PPP/PFIに関する制度の2024年度の支援対象として、「先導的官民連携支援事業」に29件、「専門家派遣によるハンズオン支援」に2件を採択した。先導的官民連携支援事業は事業手法や対象施設にモデル性がある事業について、その導入や検討、導入判断に必要な情報整備の調査費用を補助する。専門家派遣によるハンズオン支援は、国交省が委託契約したコンサルタントを派遣し、事業スキーム案の検討、サウンディング(対話)の準備や実施などを支援する。それぞれ42件、3件の応募があった。
情報元:建設通信新聞
▽2024.4.9
国交省/4月22~23日に官民連携手法発表会/民間提案から5テーマ77件提案
国土交通省は官民連携手法に関する民間提案を地方自治体などと共有する取り組みを本年度も実施する。22、23日に発表会「アピールタイム」をオンラインで開催。「民間提案型官民連携モデリング事業」の一環で募集していた、PPP/PFIのモデル形成に向けた民間事業者による5テーマのシーズ提案77件と、地方自治体のニーズ提案9件を発表する。情報元:建設通信新聞
国交省・プラトービュー最新版公開/作図機能など追加
国土交通省は、3次元都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を進めるプロジェクト「PLATEAU(プラトー)」のデータをブラウザで閲覧できる「PLATEAUVIEW」の最新版を公開した。任意の場所に好きな形状や高さで建築物を作図できる機能などを追加した。「PLATEAUVIEW3・0」には作図機能のほか、グーグルのストリートビューで街の写真を確認しながら、3D都市モデルを体験できる機能を設けた。
太陽光のシミュレーション機能や人口などの統計情報をヒートマップで表現する機能も追加した。
情報元:建設通信新聞
▽2024.4.5
国交省/24年度PPP協定パートナーを選定/民間75者、官民連携普及に無償協力
国土交通省は同省と「PPP協定」を締結し、地方自治体へのPPP/PFIの普及に無償協力する民間事業者75者を選んだ。協定の内容別内訳は▽データベース(DB)パートナー3者▽セミナーパートナー8者▽金融機関パートナー15者▽個別相談パートナー49者。2023年度から1者減った。協定期間は25年3月31日まで。官民連携事業の普及に向けて、各地方自治体への無償支援を依頼する。DBパートナーは官民連携に関する情報を閲覧できるDB、セミナーパートナーは、自治体や地場企業が参加する官民連携セミナーを開催する。金融機関パートナーと個別相談パートナーは官民連携に関する相談に無償で対応し、勉強会も開催する。
情報元:建設工業新聞
▽2024.4.4
内閣府/インフラ再構築にPPP・PFI活用へ/先行事例水平展開へ調査実施
内閣府はインフラの統廃合や集約化、施設・管理の共同化などインフラの再構築に向けた取り組みを効果的に進める手法としてPPP/PFIに注目している。行政の財源や人材不足に対応するため、▽分野横断型▽広域型-の2本柱で推進。先行事例を水平展開するため、調査しノウハウや知見を取りまとめる。事業形成に向けた先行事例の調査研究を実施しており、3月29日に中間報告を示した。今後もヒアリングやアンケートを実施し、12月に成果を固める。情報元:建設工業新聞
経済財政諮問会議/立地適正化計画公表市町村500超、インフラ整備など効率化進展
インフラの整備や維持管理を効率化する国や地方自治体の取り組みが進展していることが、内閣府の経済・財政一体改革推進委員会の点検・検証で分かった。公共施設等総合管理計画を見直したり、費用の見通しを公表したりする自治体が大幅に増加。立地適正化計画を公表した市町村は2023年3月で500団体を超え、コンパクト・プラス・ネットワークを意識した対応が進んでいる。PPP/PFIを推進する動きも目立つ。PPP/PFIは、優先的検討規定に基づく新たな事業を検討した自治体が18年3月の19団体から23年3月では183団体に増えた。導入可能性調査などを実施した人口20万人未満の自治体は23年3月で483団体(22年3月369団体)となった。点検・検証の結果として、広域・多分野・官民の連携、新技術の活用、都市のコンパクト化と老朽化対策の推進などが必要と指摘している。
情報元:建設工業新聞
▽2024.4.3
内閣府、PPP・PFI推進アクションプランフォローアップ/22年度事業規模は3・9兆円
内閣府は2023年6月に改定した「PPP/PFI推進アクションプラン」(22~31年度)のフォローアップ結果をまとめた。アクションプランでは、PPP/PFIの事業規模を10年間で30兆円とする目標を描く。初年度の22年度単年の実績は3・9兆円だった。フォローアップの結果は、今年予定するアクションプランの改定に向けた検討などで参考にする。情報元:建設工業新聞
内閣府/自治体のPPP・PFI導入支援事業/23年度は24団体を採択
内閣府は地方自治体のPPP/PFIの導入を支援する2023年度「民間資金等活用事業調査費補助事業」の対象自治体に、24団体を採択した。導入可能性調査や公共施設の資産評価(デューデリジェンス)などで必要となる調査委託費を国費で補助する。1件当たりの上限額は1000万円とする。だが都道府県と政令指定都市は、コンセッション(公共施設等運営権)を除き、補助率を2分の1、上限額を原則500万円とする。対象自治体に対し導入可能性調査などで、コンサルタントなど専門家に調査や検討を依頼する経費(委託費)を支援する。
情報元:建設工業新聞