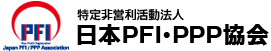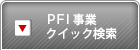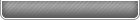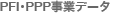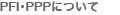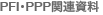PFI・PPP関連ニュース
▽2020.8.31
国土交通省と内閣府来月末にセミナー/自治体職員にサウンディングの動向紹介
国土交通省と内閣府は、PPP/PFIの導入に当たって実施されるサウンディング(官民対話)の最新動向などを情報提供するセミナーを9月30日に開く。現地参加とオンラインの2つの方法で開催し、定員は計850人程度。参加費は無料。官民連携に関心がある地方自治体の職員を対象に、18日まで参加を募集する。
定員は、東京都港区の三田共用会議所で実施する現地参加が50人程度、オンライン参加が300人程度。先着順で受け付ける。
情報元:建設通信新聞
京王電鉄・南大沢駅周辺/スマートシティ化議論/都、今秋に協議会
東京都は今秋、京王電鉄相模原線の南大沢駅周辺地区(八王子市)のスマートシティー化に向けた「南大沢スマートシティ協議会(仮称)」を立ち上げる。同市や地元商店街、交通事業者などの参加を想定しており、先端技術の活用について検討する。20年度は同駅周辺でスマートシティー実施計画の策定や実証実験の議論を進め、21年度に取り組みの方向性を検討する。
協議会では、5G(第5世代移動通信システム)などの技術を活用したまちづくりを推進するために、必要な各種調整や合意形成のほか、専門的見地から意見などを交わす。
実施計画の策定に当たっては、南大沢地区の現況や都市構造などを整理し、都市の課題を抽出する。その上で、先端技術を活用した解決策や実証実験の実施体制などを検討。同地区におけるスマートシティーの全体像を示す。
情報元:建設通信新聞
経産省/DX加速へ研究会/検討開始、10月めどに結果
経済産業省は企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を後押しするため、課題や対策を議論する研究会を立ち上げた。デジタル分野の学識者やIT業界の有識者らで構成。27日にオンラインで初会合を開き、DX推進の全体像などで検討に着手した。実務の論点はワーキンググループを設置し議論する。10月下旬をめどに検討結果を公表する。
情報元:建設工業新聞
▽2020.8.27
政府/スーパーシティ特区/12月下旬に公募/1日に改正国家戦略特区法施行
政府は、「スーパーシティー構想」の実現に向けた手続きなどを定める改正国家戦略特別区域法の施行日を9月1日とする政令を25日の閣議で決定した。同法を所管する内閣府は、スーパーシティーに取り組む特区の公募を12月下旬に始めることを想定している。
スーパーシティーで複数の先端的サービス間のデータを収集・整理・提供するデータ連携基盤整備事業の基準も定めた。データ連携基盤の整備事業者が順守すべき基準として、API(ソフトウェアの機能共有)の仕様、取り扱うデータの種類・内容・形式、データ活用に伴う規約などをインターネットで公開し、データ提供に関して不当に差別的な取り扱いをするなどの条件を付してはならないとしている。
あわせて、スーパーシティーの基本構想について、住民など関係者の意向を確認する方法を定めた。特区に選定されたエリアの首長や特区担当大臣、民間事業者らで組織する国家戦略特別区域会議が基本構想を策定し、規制改革の事項を抽出。国への申請に向けて、公聴会や説明会で事前に区域計画と認定区域計画の案を住民らに説明するとしている。
情報元:建設通信新聞
東京都財務局/東京の都市を3D化/国交省データ基盤とも連携/参加申し込み31日まで受付
東京都は、都市の図面を3D化した新たな地図をつくるため、各種の調査・検討を通してモデルエリアの選定とパイロットマップを作成する。地図には、人流や交通など多分野にわたるリアルタイムデータを付加し、都市課題の解決や都民生活の質の向上に向けた施策検討などの基盤とする。財務局は26日、都市の3Dデジタルマップ化に向けた調査業務委託の企画提案の公募を開始した。参加申し込みは31日まで受け付ける。10月9日のプレゼンテーションを経て、委託先を選定する。履行期限は2021年3月19日。
都市の3Dデジタルマップは、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)、自動運転といった技術革新のほか、各種ビッグデータと連携して、移動、物流、防災、まちづくりなど多様な分野で都市のデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するための基盤となる。
委託では、日本国内における都市の3Dデジタルマップに関する事例を比較検討する。必要となるデータ、精度、運用コストなどを整理して、都が整備するべき3Dマップの全体像を検討する。
情報元:建設通信新聞
▽2020.8.26
北村担当相/スーパーシティ選定は来春で調整
北村誠吾地方創生担当相は25日の閣議後記者会見で、人工知能(AI)などの最先端技術を活用した「スーパーシティ構想」の対象地域を、2021年春ごろに選定する方向で調整していることを明らかにした。当初は年内の選定を目指していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で自治体側の準備に遅れが見込まれるため、スケジュールを変更する。
新たな日程では、年内をめどに公募を始め、5カ所程度を選ぶ。
情報元:建設通信新聞
▽2020.8.24
東京都/官民連携DPF実証/4テーマ6事業選定
東京都は、官民連携データプラットフォーム(DPF)のコア事業実証プロジェクトを公募した結果、4テーマ6プロジェクトを選定した。テーマは3密回避・交通混雑・バリアフリー・防災の4つ。このうち防災では、NECが協力企業とともに「風水害時の人流・SNS分析によるリアルタイム防災マップシミュレーション」を実施する。いずれのプロジェクトの実証も8111月にかけて実施する予定だ。
DPFは、行政や民間が保有するデータを持ち寄り、社会的な課題の解決や都民生活の質の向上を目指すためのプラットフォームをつくる試み。公募では、都の支援を受けながら、実際にデジタルデータを活用し各テーマの新しいサービスを実証する。
情報元:建設通信新聞
奈良県/八条・大安寺にAIタウン/検討プロポ公告
奈良県は21日、「令和2年度奈良市八条・大安寺地区周辺まちづくり検討業務委託(AIタウン検討事業・都づくり)」の委託先を決める公募型プロポーザルを公告した。同地区の一部で人工知能(AI)などを用いたAIタウンを計画。まちづくりの進め方を検討するため、スマートな都市サービスの事例を集めるとともに、将来像を具体化するため多様なメンバーを集め新しいアイデアなどを創出する「アイデアソン」の企画運営などを行う。参加表明書は9月3日、提案書は10月上旬まで受け付け、同下旬にも委託先を決める。
業務内容は▽スマートな都市サービスの検討の進め方(他事例調査、構想パートナーの選定支援)▽まちの将来像の検討(将来像の整理、アイデアソンの企画運営)▽検討会の資料作成・運営補助。
構想パートナーの募集を21年度以降に予定しており、提案募集要項案を作成する。
委託限度額は1200万円(税含む)。業務期間は21年3月26日まで。
情報元:建設工業新聞
▽2020.8.17
関東整備局/事業促進PPPが増加/不調対策で独自緩和策
関東地方整備局で事業促進PPPを活用するケースが着実に増加している。契約件数は2017年度が3件、18年度は6件、19年度は10件で推移し、20年度は手続き中を含めて既に11件(6日現在)となっている。社会的要請から今後も活用件数は増加傾向が続くと見られるが、一部で不調の発生が課題となっている。こうした状況を踏まえ、同局は20年度から独自の条件緩和策を導入した。公告作業が本格化する年度後半に向け、受注サイドの応札動向に注目が集まっている。
東日本大震災からの復興道路、復興支援道路整備を皮切りに導入が進んだのが事業促進PPPだ。効率的な事業促進を図るため、柱となる直轄職員と業務の受注者が官民パ-トナーシップを組み、双方の技術者が持つ多様な知識・豊富な経験を融合させながら事業監理を行う方式となる。
情報元:建設通信新聞
▽2020.8.7
官民連携データプラットフォーム/4テーマでWG設置/1月下旬に事業計画提示
都市やインフラに関する官民データを活用した都市課題解決に向け、東京都が立ち上げた「官民連携データプラットフォーム(DPF)運営に向けた準備会」の初会合が6日、ウェブ上で開かれた。会合では、DPFの構築に向け検討すべき項目を確認したほか、都市課題などのテーマに応じたワーキンググループ(WG)を設置することを明らかにした。8月下旬の第1回WGに向けた当初の課題には「施設系混雑」「バリアフリー」「災害」「交通系混雑」の4テーマを指定。関連するデータを保有する企業とともにデータ利活用のニ-ズや課題を話し合う。
情報元:建設通信新聞
▽2020.08.06
国交省検討会/下水道で官民連携促進/自治体ら参加
国土交通省は、「下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会」を開いた。東京や大阪など6会場をオンラインで結び、地方自治体の担当者など約110人が参加。官民連携の先行事例や、同省の取り組みを報告した。
検討会は今回で2回目。国交省水管理・国土保全局下水道部の梶原輝昭下水道企画課課長は「下水道事業を取り巻く環境が厳しさを増す中で、運営の効率化を図る有効な手段の1つとして、官民連携を推進している」とあいさつした。
情報元:建設通信新聞
日本PFI・PPP協会/不可抗力の定義示す/感染症取扱い公表/新型コロナ対応
日本PFI・PPP協会(植田和男会長兼理事長)は、『PFI事業契約における新型コロナウィルス感染症の取扱い』と『コンセッション契約(公共施設等運営権実施契約)におけるコロナウィルス感染症の取扱いについてのFAQ(よくある質問)』をまとめ、同協会のホームページで公表した。
「コロナウィルス感染症の取扱い」では、地震、洪水、地滑りといった自然災害にかかる事象や当該義務履行当事者にとって予測可能性または支配可能性のない事象(疫病放射能汚染、航空機の墜落を含む)などのうち、公共施設管理者と設置運営事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものを不可抗力要件の定義例として提示。対応策では、債務履行期限の猶予、損失・増加費用の分担などを挙げている。
情報元:建設通信新聞
▽2020.8.5
経産省・スポーツ庁/交流拠点スタジアム・アリーナ/来月14日まで第1回公募
経済産業省とスポーツ庁は、「多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ」の第1回公募を始めた。参加表明書を9月14日まで、申請書類を9月15日-10月5日に受け付ける。審査結果は2021年1月に発表する。選定された団体は、ハード整備に関する交付金の要件緩和や助成金の審査時に加点されるなどのインセンティブ(優遇措置)を受けることができる。
応募対象は、17年以降に▽スタジアム・アリーナの新設・建て替えまたは大規模改修に関する構想・計画の策定▽スタジアム・アリーナの新設・建て替えまたは大規模改修に関する設計・建設▽新設・建て替えまたは大規模改修されたスタジアム・アリーナの運営・管理――のいずれかの事業を実施している地方自治体、法人格を持つ団体、コンソーシアムなど。
情報元:建設通信新聞
▽2020.8.4
行政デジタル化 一元管理/「政府CIO」権限強化へ
政府は行政のデジタル化を進めるため、司令塔となる内閣情報通信政策監(政府CIO)の権限を強化する。各府省で足並みのそろっていないデジタル化の一元管理や国と地方のシステムの共通化を進める。2021年の通常国会に提出予定のIT(情報技術)基本法改正案に盛り込む。
政府CIOは政府全体のIT政策の司令塔として13年に設けた。内閣官房IT総合戦略室の室長政を兼務する。省庁横断でIT関連予算の一元化をめざす。今の政府CIOは大林組出身の三輪昭尚氏で18年に任命された。
情報元:日本経済新聞
▽2020.8.3
政府検討/自治体システム、仕様統一/来年、デジタル化へ新法
政府は住民記録や税・社会保険などを管理する自治体のシステムについて、標準仕様への統一を義務付ける新法を制定する検討に入った。これまで各自治体が独自仕様のシステムを構築してきたので国や自治体のデータ連携が進まず、新型コロナウイルス対応では給付金の支給遅れなどを招いた。行政のデジタル化を急ぐため、来年の通常国会への提出を目指す。
標準化が進めば、デジタルで貫徹することを前提としたシステム構築で電子申請を促進できる。企業が自治体に提出する書類の様式もそろう。システムの維持管理や改修にかかる自治体の費用負担も軽くなる。
情報元:日本経済新聞
スーパーシティ指定延期/来年3月ごろに/コロナ、準備に影響
政府は人工知能(AI)などの先端技術を活用した「スーパーシティ」構想について対象区域の指定を延期する。12月の予定を2021年3月ごろに改める。新型コロナウイルスの収束が見通せず、応募する地方自治体で事業計画の作成などの準備が間に合わない可能性が高いためだ。
政府は近く開く国家戦略特区諮問会議で新しいスケジュールを決定する。公募期間は12月末から21年2月ごろまでを想定する。
スーパーシティは改正国家戦略特区法に基づくものだ。行政手続きや観光、交通など幅広い分野で利用者のデータを連携させるのを規制緩和で認める。自治体は応募前に参画企業の決定や住民への説明会、パブリックコメントなどを実施する。
情報元:日本経済新聞