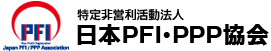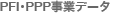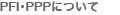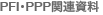PFI・PPP関連ニュース
▽2025.5.14
自民水道・下水道事業促進議連が総会/予算の増額確保など求める決議採択
自民党の国会議員でつくる「水道事業促進議員連盟」と「下水道事業促進議員連盟」の両議連(会長・田村憲久衆院議員)は13日、東京・永田町の党本部で合同総会を開き、上下水道予算の増額確保などを求める決議を採択した。決議内容は▽2026年度当初予算での上下水道関係費を増額確保と骨太の方針への重要性位置付け▽大口径上下水道管の老朽化対策やリダンダンシー確保の集中的な実施▽急所となる基幹施設や重要施設の耐震化▽資材価格、人件費の上昇に対する追加の予算措置▽さらなる広域化、ウオーターPPPなどの官民連携、デジタル技術などの開発・実装、分散型システム導入▽国際水ビジネスの積極展開を推進▽上下水道の脱炭素化や下水道汚泥の活用、下水道処理場などの未利用地活用など省庁間連携強化▽人材育成推進-など。
情報元:建設工業新聞
▽2025.5.8
内閣府/PPP・PFI推進アクションプラン原案、人口5万人以上自治体で活用促進
内閣府民間資金等活用事業推進室は8日、政府が決定するPPP/PFI推進アクションプラン(2025年改定版)の原案を明らかにした。地方自治体の支援強化、民間事業者の環境改善、人口5万人以上の自治体にPPP/PFI活用を促す方針をうたう。事業の検討開始から事業者決定までの期間短縮や負担軽減を進める考えなども明記する。同推進室は手続きの効率化に関するマニュアルを25年度末に作成する。25年改定版は、16日のPFI推進委員会の議論を経て、政府のPFI推進会議(会長・石破茂首相)が決定する。
情報元:建設工業新聞
内閣府/実施方針に対価改定基準時点明示/PPP・PFIガイドライン改正
内閣府民間資金等活用事業推進室は、PPP/PFIに関する各種ガイドラインの改正内容をまとめた。民間事業者が適正な利益を得られる環境を整えるのが狙い。契約ガイドラインを改正し、サービス対価の改定基準時点を事業の実施方針などに明示するのが望ましいことを明記。適当な物価指数の選択が難しい場合であっても、採用する指数について丁寧に検討していくことなどをうたう。物価変動に伴い、契約変更や事業者選定の協議が難航したり、計画の再検討によって進行が遅れたりしているPPP/PFI事業がある。同推進室はガイドラインの改正や通知・事務連絡の発出などを行ってきたが、さらに対応する必要があると判断した。ガイドラインなどの改正はPFI推進委員会で審議し、政府のPFI推進会議(会長・石破茂首相)に諮る。
情報元:建設工業新聞
内閣府/PPP/PFI優先検討規程/対象自治体を拡大
内閣府は、PPP/PFIの導入を促す自治体を広げる。PPP/PFIの優先的検討規程の策定を求める自治体の規模を現行の10万人以上から5万人以上にする。優先的検討規定の準則を定める指針を改定し、PPP/PFIをさらに推進する。8日に開いた民間資金等活用事業推進委員会計画部会で指針の改定案を示した。
現行指針の発出以降、優先的検討規程を策定した自治体数は着実に増加。人口10万人以上20万人未満の市区では約6割が策定しており、PFI事業実施方針の公表件数も伸びている。PPP/PFIの導入をさらに広げるため、指針を改定し、優先的検討規程の策定・運用を求める自治体の人口を10万人以上から5万人以上にする。
情報元:建設通信新聞
▽2025.5.8
国交省/地域生活圏形成リーディング事業調査業務公募/5月26日まで参加受付
国土交通省は「地域生活圏形成リーディング事業(調査業務)」の公募を始めた。地域の課題解決と魅力向上を目指す「地域生活圏」の形成に向け、先導的な取り組みを行っている官民連携プラットフォーム(PF)を支援する。応募期間は26日まで。審査を経て6月下旬に採択を決める。事業期間は2026年2月27日まで。支援額は▽官民パートナーシップによる主体の連携▽分野の垣根を越えた事業の連携▽行政区域にとらわれない地域の連携-の三つの条件を満たす場合、補助率3分の2。主体の連携と事業の連携の二つの場合は補助率2分の1。上限額はいずれも3000万円(税込み)。
情報元:建設工業新聞
▽2025.5.7
文科省/自治体のコンセッション案件形成支援/文教施設に導入促進
文部科学省は、文教施設の整備・運営を検討している地方自治体などに官民連携手法の採用を促す。2025年度はコンセッション(公共施設等運営権)方式を含めたPPP/PFI事業を計画する自治体など6者を選定し、導入検討の勉強会や専門家派遣による伴走支援に取り組む。先導性のある事業を支援対象に選ぶ。取り組みの関連業務をデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーに委託して実行する。25年度の「文教施設における多様なPPP/PFIの先導的開発事業」として、伴走支援などを行っていく。民間事業者の資金や創意工夫を生かすため、コンセッション方式の活用を基本としたい考え。高い収益性が見込めない文教施設についても専門的な知見からの伴走支援などによって、PPP/PFIの導入と案件形成を進める。
情報元:建設工業新聞
国交省/PPPパートナー/5月16日まで募集
国土交通省は、2025年度のPPPパートナー募集を16日まで受け付ける。認定期間は6月1日から27年5月31日まで。5月下旬に審査し、同月末に結果を通知する。
情報元:建設通信新聞
▽2025.5.2
国交省の官民連携モデリング導入調査/5月23日まで事業者募集
国土交通省は、民間提案で自治体の課題解決を目指す「民間提案型官民連携モデリング事業」について、自治体への導入検討を調査する民間事業者を23日まで募集する。同事業は国交省の所管分野の官民連携事業について、自治体と民間の提案をマッチングして課題解決を目指す取り組み。優れた民間提案を基にモデルとなる新たな官民連携手法を国交省の委託調査で構築し、全国に横展開する。
調査期間は2026年2月19日まで。業務規模は1件当たり最大1000万円程度。選定件数は10件を予定している。
情報元:建設通信新聞
▽2025.5.1
内閣府/違いや予算措置など明確化/PFI指標連動方式の考え方改定
内閣府民間資金等活用事業推進室は4月30日、PFI事業の「指標連動方式」の基本的な考え方を改定する方針を明らかにした。同方式は性能発注が前提で、サービス水準の指標の達成状況に応じて対価を支払う。改定に当たって類似するほかの方式との違いや、活用できる場面を明らかにし、入札説明書への記載方法、サービス対価を増額する場合の予算措置などを明記する。改定に当たっては、料金徴収する業績連動方式とプロフィットシェア/ロスシェア、料金徴収を伴わない指標連動方式、委託などによる成果連動型民間委託契約方式(PFS)の違いを整理する。混合型PFIやコンセッション(公共施設等運営権)は、サービス対価と料金徴収とで方式が異なることなども説明する。
情報元:建設工業新聞
内閣府/LABV方式活用で解説書案/自治体が土地など現物出資
内閣府民間資金等活用事業推進室は、公有資産を現物出資する地方自治体などと、資金出資する民間事業者がまちづくりなどに取り組むLABV(官民共同事業体)方式を活用するための解説書案をまとめた。事業スキームや優位性などを示した。公共施設の集約や跡地活用に取り組む自治体などに普及させたい考え。事業者の入れ替えや懸案事項に関する追記を検討し、今夏の策定を目指す。4月30日のPPP/PFI推進委員会事業推進部会(北詰恵一委員長)で案を説明した。LABVは英国のPPPの手法の一つ。連鎖的な土地開発などを想定している。国内に事例が2件あり、案は山口県山陽小野田市のプロジェクトをモデルに、ヒアリングなどを踏まえて内容を固めた。
情報元:建設工業新聞