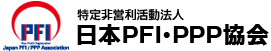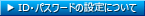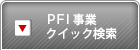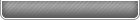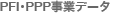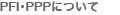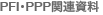PFI・PPP関連ニュース
▽2021.5.31
国交省/BIMモデル先導事業者型で7件
国土交通省は、実際の建築プロジェクトでBIMを試行して導入メリットの検証などに取り組む事業者を支援する「BIMを活用した建築生産゜維持管理プロセス円滑化モデル事業」で、2021年度に募集する8タイプのうち先導事業者型の7件を採択した。16件の応募があった。中小事業者BIM試行型とパートナー事業者型は、今後採択する。
採択した提案と事業者は次のとおり。
▽木造住宅における、BIMとクラウドサービスを用いたCDEとECIの効果検証・課題分析=アンドパッド、小林・槙デザインワークショップ、DN-Archi、長谷川萬治商店、長谷萬、慶應義塾太学▽VRモックアップの効果検証と維持管理BIMの課題分析=梓設計、戸田建設、ハリマビステム▽「Life Cycle Consulting」発注者視点でのBIM・LCCに関する効果検証・課題分析=日建設計、荒井商店。
▽技術研究施設におけるBIMモデルを用いた維持管理業務効率化等の検証=奥村組▽建材と施工の電子商取引に向けたBIMデータ連携の効果検証・課題分析=スターツアセットマネジメント▽業務効率及び発注者メリットを最大限に創出する「役に立つBIM」の効果検証=大和ハウス工業、フジタ▽建築のライフサイクルを通した発注者によるBIM活用の有効性検証=日建設計コンストラクション・マネジメント、日本郵政。
情報元:建設通信新聞
▽2021.5.26
国交省が無電柱化推進で新計画策定/5年で4千キロ事業化/コスト削減へ新技術活用
国土交通省は新たな無電柱化推進計画を策定した。新設電柱を増やさない、徹底したコスト縮減を進める、無電柱化事業をさらにスピードアップの8つの取り組み姿勢を打ち出した。経済産業省や総務省、電線管理者などの関係者と連携し、2021-25年度の5年間で約4000キロの無電柱化事業に着手することを目標に設定している。
新設電柱を増やさず、緊急輸送道路では減少させる。具体的には、電柱が毎年7万本増えているため、新設電柱の増加要因を調査・分析し、要因ごとに関係者が役割分担した上で、削減に向けた対応方策を21年度内にまとめる。
無電柱化の完了までには7年がかかることから、包括発注、PPP活用、一括施工発注を含む発注の工夫や、民間技術の活用促進、地下情報のデータベース化などにより、特殊な現場条件がある場所を除いて事業期間を平均4年に縮める。
情報元:建設通信新聞
平塚市/公共施設の個別計画策定/212施設対象、10年で300億円
神奈川県平塚市は「平塚市公共施設等個別施設計画」を策定した。計画的に施設の総量縮減や長寿命化に取り組むことで、財政負担の軽減や平準化を図る。庁舎や学校、福祉施設など212施設、合計延べ床面積2万9219平方メートルが対象。おおむね5年周期で見直し、10年以上の計画になるよう更新する。想定事業費は今後10年間で約300億円と試算している。
情報元:建設工業新聞
▽2021.5.25
FJISSと国交省下水道部/官民連携へ共同検討を/強靭化・脱炭素化も議論
持続可能な社会のための日本下水道産業連合会(FJISS、野村喜一会長)は、国土交通省下水道部との意見交換会をウェブ会議形式で開き、下水道事業に適した官民連携事業スキームの集中的な検討を官民共同で進めるよう求めた。また、災害対策では内水氾濫防止に向けた流域対策の実装や、入札契約制度の見直しを含め発災時の迅速な復旧に向けた体制構築などを提案し、今後の政策検討への反映を求めた。
この中で、下水道事業に適した官民連携の新たな事業スキームや民間ノウハウを発揮しやすい「入札手続き・評価方法・リスク分担」について、官民共同の検討組織を設置して集中的な検討を展開するよう要望したほか、下水道のDX(デジタルトランスフォー一メーション)推進での情報のオープン化や新技術導入促進による維持管理の効率化、下水道事業運営の最適化に向けてアセットマネジメントを促す仕組みの構築も提言した。
情報元:建設通信新聞
▽2021.5.24
PPP/PFI支援対象を決定
国土交通省は、PPP・PFIに関する三つの支援制度で、2021年度第1次募集の支援対象を決定した。先導的官民連携支援事業は、2タイプあるうち事業手法検討支援型のみを対象に、6月16日まで第2次募集の申請を受け付けている。
情報元:建設通信新聞
▽2021.5.20
19年度契約PFI/地域企業の参画率87%/代表企業割合は47%
内閣府は、2019年度に契約を結んだ地方自治体などのPFI事業を対象に、地域企業の参画状況をまとめた。地域企業が事業者のグループに1社以上参画している事業の割合は87%、地域企業がグループの代表企業を務める事業の割合は47%だった。過去3年分の状況をみると、どちらも同水準で推移している。
事業を実施する都道府県に本社が所在する企業を地域企業と定義し、事業主体が国などの事業とコンセッション方式を除く教育・文化20事業、健康・環境8事業、産業2事業、まちづくり13事業、庁舎・宿舎2事業、その他2事業の計47事業を調べた。
情報元:建設通信新聞
▽2021.5.19
九州整備局/Park-PFI海の中道海浜公園/3月に運営開始/事業認定で7月着工
九州地方整備局は、Park-PFI(公募設置管理制度)を導入する「海の中道海浜公園官民連携推進事業」で、公募設置予定者に特定した海の中道パーク・ツーリズム共同事業体の事業計画(公募設置等計画)を適当と認定した。7月ごろに着工し、2022年3月の運営開始を予定している。Park-PFI事業による国営公園の開業は、同事業が国内初となる見込み。
同事業体は、三菱地所を代表企業に、積水ハウス、公園財団、オープン・エーで構成する。「海の中道パーク・ツーリズム」を事業コンセプトに「滞在型レクリエーション拠点」を整備する。計画施設は、球体テントなどの宿泊施設や立体アスレチック、レストラン、厩舎・放牧地などの公募対象公園施設(約2万5000平方メートル)、屋内遊戯施設や大屋根下広場などの特定公園施設(約7000平方厨メートル)で構成する。
情報元:建設通信新聞
▽2021.5.18
会計検査院、国のPFI事業で検査報告書/VFM算定に問題点/内閣府に指針改定の検討求める
会計検査院は、2018年度末までに国が実施したPFI事業を対象とする検査の報告書をまとめた。一部のサービス購入型事業でVFM(バリュー・フォー・マネー)の算定と評価に問題があると指摘し、各府省などは適切に算定した上でPFI事業の実施を判断する必要があるとの所見を示した。VFMガイドラインの趣旨が十分に理解されていないことが一因にあるとして、内閣府にガイドラインの改定などを検討するよう求めた。
PFI事業を選定する際の評価で、PSC(従来手法による財政負担)とPFT方式のLCC(ライフサイクルコスト)を算定する条件が一致せず、それらの比較が不適当な状態になっていた。金利情勢が割引率に十分反映されなかったことで、VFMが大きく算定され、PFI方式の経済的な優位性が高く評価された可能性があったとしている。
情報元:建設通信新聞
つくば市/スーパーシティ構想提出/インフラ管理にSIB導入
茨城県つくば市がスーパーシティ構想を内閣府に提出した。「スーパーサイエンスシティ」と銘打ち、IoT(モノのインターネット)や人工知能(AI)、AR(拡張現実)などデジタルツインの関連技術を駆使。高度な防災・インフラサービスの実現、先進の医療や行政、交通、物流サービスの提供などを目指す。連携事業者として筑波大学こをはじめとする教育・研究機関、鹿島や安藤ハザマら民間企業など合わせて50者が協力する。
行政と交通、物流、先端医療・介護、防災・インフラの5分野でさまざまな取り組みを展開する。防災・インフラ分野では金融市揚から資金を調達し公共施設の維持管理に充てる「ソーシャル・インパクト・ポンド(SIB)」の導入を目指す。インフラの維持管理に成果連動型包括管理手法を採用し、コスト削減や効率的な高度な業務実施につなげる。
情報元:建設工業新聞
▽2021.5.13
デジタル庁9月発足/建設業法など押印廃止/関連法案が成立
デジタル庁設置法を柱とするデジタル改革関連法が、12日の参院本会議で可決、成立した。菅義偉首相の看板政策であるデジタル改革で、司令塔組織となるデジタル庁が9月1日に発足する。「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の規定により、建設業法や建築士法を含む48本の法律で定める押印手続きが廃止となる。
デジタル庁は、内閣総理大臣をトップとする内閣直属の組織とし、デジタル太臣を置く。関係行政機関の長に対する勧告権など強力な総合調整機能を有する。デジタル社会形成の施策策定に関する基本方針の企画立案・総合調整、重点計画の作成・推進、国の情報システム整備・管理に関する事業の統括監理、予算の一括計上などを担う。民間から採用する人材を含め、職員数500人規模でスタートする。
法律48本のうち、国交省所管は建設業法、建築士法、建設リサイクル法など17本。建設業法は、見積書の電子交付と、特定専門工事制度に基づく元下間合意文書の電子化に関する規定も追加した。これにより、民間同士の手続きを含めて建設業に関するすべての手続きの電子化が可能になる。
情報元:建設通信新聞
▽2021.5.7
内閣府ら4省/スマートシティガイド作成/導入効果など解説
内閣、総務、経済産業、国土交通の4府省は、地方自治体や地域協議会、エリアマネジメント団体など向けの手引き書として、『スマートシティガイドブック』(第1版)を共同で作成した。先行事例の成功・失敗体験を踏まえ、スマートシティーの意義・必要性、導入効果、進め方などを整理している。
情報元:建設通信新聞
関東経産局/地域企業のデジタル化支援/長岡市、松本市と協定
関東経済産業局は、地域企業の成長を目的に自治体の産業振興と地域経済の活性化を支援する包括協定を新潟県長岡市、長野県松本市と締結した。地域の企業の成長や経済分野の課題解決に連携して取り組み、企業のデジタル化やイノベーションの創出を促す。覚書の交換式は長岡市は4月26日、松本市は同28日に開いた。
情報元:建設工業新聞