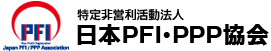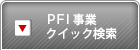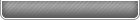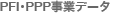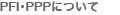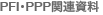PFI・PPP関連ニュース
▽2021.9.30
柏の葉スマートシティにAIカメラ/リアルタイムに画像分析
UDCKタウンマネジメントと三井不動産は、干葉県柏市の柏の葉キャンパス駅周辺に、エッジAI(人工知能)力メラを29台導入し、住民に安心・安全・快適な暮らしを提供する新たなエリアマネジメント活動を始める。クリューシステムズがAIカメラを提供し、ニューラルポケットが画像解析を担当する。
今回の試みでは、屋外公共空間にAIカメラを設置し、リアルタイム画像分析によって通行人の異常行動(倒れる、うずくまる、凶器所持など)や立ち入り検知、人流分析を実施する。撮影映像は力メラ内蔵のAIで即時分析・即時破棄する。分析データは特定の個人を識別できない形に加工し、プライバシーを侵害するようなデータは取得・保管しない。29台のAIカメラを街区に設置するタウンマネジメントの取り組みとしては、国内最大規模になるという。
情報元:建設通信新聞
秋田市/公共施設等総合管理計画見直し案/更新費用は年平均165億円
秋田市は29日、将来的な財政負担の軽減や標準化を目的に市が保有する公共施設の維持管理方針を定める「公共施設等総合管理計画」(2017〜26年度)の中間年度見直し案を公表した。過去5年間の維持補修費の実績や施設保有総量の縮減などを踏まえ、更新費用や効果額などを修正。40年間に施設更新に要する費用は年平均165億円と見積もった。継続して公共施設の統廃合や複合化などによる保有量縮減を図る考えを示した。
今後、投資的経費の確保が困難になっていくとの推測から市は更新費用をさらに縮減していく考えを示した。マネジメント方針は現状を維持し、施設の統廃合や複合化などによる保有量見直しや、長寿命化による投資的経費の削減を図る。PPP/PFIなど民間活力導入による効率化を推進する方針も継続する。
市は年内にも総合管理計画を策定し、これに基づき▽公共施設マネジメント推進体制の構築▽マネジメントサイクルの確立▽財源確保▽個別施設計画の見直し▽民間活力の積極活用-などの取り組みを進めていく。
情報元:建設工業新聞
▽2021.9.24
矢板市/文化スポーツ施設未来技術導入/22日まで参加受付
栃木県矢板市は、文化スポーツ複合施設への未来技術の導入に向け、RFI(情報提供依頼)を実施する。参加申し込みと情報提供資料は10月2日まで受け付ける。
矢板市文化会館、矢板公民館、矢板市体育館を複合化した「(仮称)矢板市文化スポーツ複合施設」を、既存のとちぎフットボールセンター(末広町49-1、敷地1万9181平方メートル)内に整備する。未来技術を導入し、競技力向上や健康データの見える化を目指す。今回のRFIでは、未来技術の導入に向けた検討の具体化を目的に、事業者から情報提供を求める。
現時点で▽5Gを活用したスポーツ・文化活動の映像配信▽トレーニング環境の整備とスポーツドッグ(測定・分析・カウンセリング)事業▽健康ステーション事業▽地域・観光情報サービス事業▽予約管理システム導入事業――を想定している。
情報元:建設通信新聞
▽2021.9.16
内閣府/PPP・PFI行政実務専門家/派遣の取り組み開始
内閣府は、PPP/PFIの行政実務経験を持つ地方自治体の職員がPPP/PFI事業を検討する自治体に対して助言する取り組みの運用を始めた。内閣府が認定・登録したPPP/PFI行政実務専門家を派遣し、庁内の体制整備、事業の企画立案・事業化、契約手続きなどを支援する。
具体的な支援の内容は、庁内の推進体制構築、検討ルールの整備、個別事業の企画立案、事業の企画から実施までのスケジュール作成・工程管理、予算確保に向けた関係部局との調整、実施方針策定、サウンディング調査、契約事務、事業者との契約調整、議会対応など。
情報元:建設通信新聞
▽2021.9.15
自治体PPP支援/日本経済研と八千代エンジ
内閣府は、「令和8年度茨城県行方市及び千葉県八街市におけるPPP/PFI手法優先的検討規定策定・運用に関する調査検討支援業務」「令和3年度長野県諏訪市及び愛知県豊明市におけるPPP/PFI手法優先的検討規定策定・運用に関する調査検討支援業務」を総合評価一般競争入札した結果、行方市・八街市を935万円(税込み、以下同)で日本経済研究所、諏訪市・豊明市を748万円で八千代エンジニヤリングに決めた。
これらの業務では、PPP・PFI手法の適用を従来調達手法に優先して検討する際に使う「優先的検討規定」の策定を支援する。委託期間は2022年3月25日まで。
情報元:建設通信新聞
近畿整備局/三宮バスターミナル整備/民活導入へウェブ調査/17日から
近畿地方整備局はJR三ノ宮駅近くの再開発ビルに計画しているバスターミナル(神戸市中央区)の維持管理・運営について、コンセッション(公共施設等運営権)制度の導入を検討している。再開発会社が建設する高層ビルのうち、低層部を国が区分所有し、民間事業者と連携して施設を整備する。近畿整備局では民間事業者の参画意向を確認するため、17日からウェブ方式でアンケートを開始する。
バスターミナルは駅周辺に分散する中長距離のバス停を集約し、交通結節機能を強化するもので、再開発ビルの1~3階部分に整備する。地下2階の車寄せなどを含めた総面積は約6800平方メートル。1階がバス乗降場、2〜3階が待合いとチケット売り場、店舗を想定している。
情報元:建設工業新聞
▽2021.9.9
北九州市/スーパーシティ構想/17日まで追加提案
北九州市は、国が進めるスーパーシティ型国家戦略特別区域の公募について、規制改革に関する追加提案募集を始めた。提案書は17日まで企画調整局地方創生推進室で受け付ける。採用案は30日までに提案者に通知する。提案者がことし2月に選んだ参画事業者でない場合、参画意向申出書の提出を求める。10月中旬に参画事業者候補を公表する。
提案資格は、個人を除く企業か研究機関、団体。提案内容は、市が国に提出したコンセプトや基本方針に沿い、規制改革が実現した場合に主体的に先端的サービスの実証・実装に取り組む意思、実現可能性が高いもの。現行では実現不可能か困難で、実現するための規制・制度改革を具体的に示した提案とする。
情報元:建設通信新聞
▽2021.9.8
広島県/広島デジフラ構想推進支援/国際航業に決まる
広島県は、「令和3年度広島デジフラ構想推進支援業務」の公募型プロポーザルで、国際航業を最優秀提案者に選定した。今後、契約に向けた協議を進め今月中の契約締結を目指す。履行期間は2022年3月22日まで。事業予算(費用の上限額)は1000万円(税込み)。
県では、建設分野の調査、設計、施工から維持管理のあらゆる段階で、デジタル技術を最大限に活用し、官民が連携して公共土木施設などのインフラ整備をより効果的・効率的にマネジメントしていく。3月には「広島デジフラ構想」として、目指す姿や具体的な40項目の取り組みをまとめた。
情報元:建設工業新聞
関東整備局/事業促進PPP/契約率が大幅改善/受注制限緩和など奏功
関東地方整備局が発注している「事業促進PPP(官民連携事業)」業務の委託先選定手続きで、契約率が大幅に改善している。従来は厳しい受注制限などがあり、プロポーザル方式で発注しても委託先が決まらないケースが多かった。関東整備局は事態を打開するため、2020年度に発注条件などを見直した。19年度に5割以下だった契約率は、21年度に入り6月末時点で約9割に上昇している。今後も受注者にインセンティブを与える施策を展開していく。
事業促進PPPは民間のノウハウを活用し、大規模公共事業の円滑な推進を図る目的で発注している。全体計画の整理や業務の調整、施工管理などを委託する。
情報元:建設工業新聞
▽2021.9.7
経産省とスポ庁/交流拠点スタジアム・アリーナを募集
経済産業省とスポーツ町は6日、20221年度の「多様な世代が集う交流拠点としてのスタジアム・アリーナ」選定に向けた募集を始めた。参加表明書は10月12日まで、申請書類を10月12日-11月1日の期間に受け付ける。募集に関する説明会は15日に開く。申請書類を11月中旬から22年1月中旬にかけて選定要綱に基づき審査し、同年2月に審査結果を公表する予定。
情報元:建設通信新聞
呉市/まちづくり構想基礎調査/日本工営に優先交渉権
広島県呉市は、「まちづくり構想策定に向けた基礎調査業務」の公募型プロポーザルで、日本工営を優先交渉権者に選定した。近く契約する。業務の委託上限額は400万円(税込み)。履行期間は2022年3月13日まで。
市では、人口減少、少子高齢化が進行する中、豊かで持続可能な地域社会の実現に向け、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進によるスマートシティーの実現、ICT(情報通信技術)等を活用した新たな事業の創出や観光の振興、防災・減災の街づくりに取り組むことにしている。今回委託する業務は、こうした課題の解決に資する街づくりの取り組みを検討するとともに、その実現のため、防衛省の補助事業である「まちづくり構想策定支援事業」の活用に向けた調査・検討資料を作成する。
情報元:建設工業新聞
▽2021.9.6
日本工営の支援システム/インフラ維持管理効率化・高度化/自治体負担を軽減
日本工営は、道路などのインフラ維持管理に寄せられる住民からの要望・意見とその対応を自治体管理者と維持工事受託者など関係者間でクラウド共有できる維持管理情報支援システム「Manesus(マネサス)」に、道路の日常管理までを含む多業務のマネジメント支援機能と、よリフレキシブルな活用ができる管理機能を追加拡充した。同社が4月から参画する東京都府中市全域での市道路等包括管理事業でも全市の住民要請を受けるコールセンター業務管理に同サービスを活用、安定的で効率的な運用を確認している。
このサービスは、インフラの老朽化が進む中、道路などのメンテナンス要望に対応する自治体関係者間の業務効率化・負担軽減を目的に、「要望受付〜措置完了」までの一連の各種作業から事務手続きをクラウド上で一元管理するビジネスモデルのバックエンドサービス。2020年10月のリリース以降、既に複数の自治体で活用され、管理者の負担軽減、時間短縮などが認一められている。
情報元:建設通信新聞
東京・世田谷区/公共施設等総合管理計画を改定/コロナ禍で財源有効活用/DX推進も
東京・世田谷区は、保有施設の維持や修繕の方針を示す「公共施設等総合管理計画」(計画期間2017〜26年度)を改定する。工事積算単価の上昇や新型コロナウイルスの流行などを踏まえ、限られた財源をより有効に活用。利用率が低い施設の対処、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進などを計画に盛り込む。
3日の区議会に同計画の改定案を報告した。施設の整備・維持に必要な費用は策定時に設定した目標「年間約550億円」を大きく上回る見通し。区は19年8月時点で年間の整備・維持費を約603億円と試算。財政への影響が大きくコロナ禍の対応も続くと見て、試算値よりも約20億円少ない580億円程度に設定し直す。
新たな重点方針には▽学校を中心とした複合化整備の推進▽効果的・効率的な施設整備の徹底▽既存施設の利用機会の拡充――の三つを掲げた。複合化は区有施設の過半数を占める学校を中心に推進する。維持費を削減しつつ、複合化で空いた士地の有効活用も検討する。敷地状況に伴う追加工事などでコスト増が見込まれるが、設計・運営の工夫で抑制する。
情報元:建設工業新聞
函館市/公共施設等総合管理計画改定/更新費203億円削減へ
北海道函館市は、将来的な財政負担の軽減や平準化を目的に市が保有する公共施設の維持管理の考え方を整理した「函館市公共施設等総合管理計画」を一部改定した。施設保有総量の縮減などを踏まえた40年間の更新経費や効果額などを追加。今後10年で公共施設の総量を3万9000平方メートル削減し、更新経費を203億50百万円縮減する目標を設定した。
情報元:建設工業新聞
▽2021.9.3
文科省/文教施設へのPPP・PFI/先導的開発事業を実施/2自治体程度採択
文部科学省は、自治体の文教施設分野で多様なPPP・PFI事業の案件形成を推進するため、PPP・PFI事業の導入に向けた課題の整理や手法の開発、具体的な検討を行う自治体を支援する先導的開発事業を2022年度も実施する。22年度予算の概算要求には、必要経費2600万円を盛り込んだ。
先導的開発事業は、▽人口20万人未満の小規模自治体でのPPP・PFI事業▽文教施設などの集約・複合化に関するPPP・PFI事業▽施設の維持管理に関する包括的民間委託事業-の3類型が対象になる。
事業を手掛ける自治体を募り、2自治体程度を採択する。事業には、自治体が地域や施設の特性などを踏まえて導入可能な施設の抽出・選定などを実施する事業検討段階の「事業の発案」と、VFM(バリュー・フォー・マネー)の算定や官民リスク分担など事業スキーム開発の「具体化の検討」がある。事業の成果を全国に発信して、ほかの自治体に多様なPPP・PFI事業導入の参考にしてもらう。
情報元:建設通信新聞
文教施設包括的民間委託手引き/日本経済研と契約
文部科学省は、自治体文教施設分野での多様なPPP・PFIの導入促進に向け、民間企業の創意工夫による効率的な維持管理、運営を取り入れ、複数の施設を包括的に委託する『包括的民間委託などの導入に関する実務的な手引き(仮称)』の作成業務委託先を日本経済研究所(東京都千代田区)に決めた。8月30日に906万8185円(税込み)で契約した。手引きは2022年3月に策定する。
また、手引きの周知や事例の紹介など文教施設のPPP・PFIに関係するオンラインセミナーも、自治体や企業の担当者を対象に同3月末までに開く。
情報元:建設通信新聞
▽2021.9.1
デジタル庁が発足/600人規模でスタート/約200人が民間人材/官民連携でデータ活用環境整備
菅政権が推し進める「デジタル改革」の司令塔になるデジタル庁が1日に発足する。コロナ禍で露呈した行政手続きのデジタル化の遅れを解消するため、データが徹底活用できる環境整備に官民連携で取り組む。インフラや防災などの分野でもデータ連携の基盤構築や地方自治体を含めた行政サービスの効率化などを目指していく。
内閣直属の組織となるデジタル庁は菅義偉首相をトップに、担当の「デジタル相」、事務方トップの「デジタル監」を置く。1日にデジタル相の任命、デジタル監など幹部人事を閣議決定する。国民向け行政サービスの開発部門など4グループを設ける。職員数は600人規模でスタート。うち約200人がITなどに精通した民間人材で、各省庁から350人超の職員が集まる。国土交通省からはIT総合戦略室に出向している職員がデジタル庁に異動。土木系の技術職員が防災、スマートシティーを所管する参事官に就く。
デジタル庁は分野間でデータ連携する基盤やルールづくりを担う。インフラや防災、スマートシティーなどを重点分野に設定。デジタル庁と関係省庁が協働し、プラットフォームを2O25年までに実用化する。インフラ分野では国交省が先行して構築している「国土交通データプラットフォーム」を核とした情報基盤の整備を検討する。
情報元:建設工業新聞