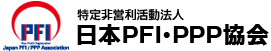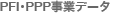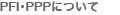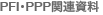PFI・PPP関連ニュース
▽2024.2.29
国交省 無電柱化の推進方針/市街地優先で集中整備
国土交通省は、無電柱化の推進に向けた今後の取り組み方針をまとめた。これから管路を整備する緊急輸送道路のうち、特に市街地区間を優先区間に抽出して集中的に投資する。優先区間の明確化により管路整備をさらに促進し、早期の電柱撤去を目指す。28日に開いた「無電柱化推進のあり方検討委員会」で示した。
無電柱化の取り組みとして、第1期計画が始まった1986年度から2023年度までに約9900㎞で管路整備が完了した。今後の管路整備予定延長は第7期計画以前に着手した約2200㎞と、25年度までの第8期計画で着手する約4000㎞の計6200㎞となる。この中の緊急輸送道路約4600㎞のうち、市街地区間約3500㎞で優先区間を明確化し、集中的な管路整備を進めていく。
優先区間は、地方ブロック無電柱化協議会などで緊急輸送道路や地域防災計画の観点から防災上重要性の高い区間を抽出する。例として「高速道路ICから広域防災拠点間」「広域防災拠点から防災拠点間」「防災拠点と防災拠点間」の三つを挙げている。
情報元:建設通信新聞
▽2024.2.22
内閣府、国交省/PPP・PFI協定締結対象を募集/地域の官民連携基盤支援
内閣府と国土交通省は全国でPPP/PFIの案件形成促進策として、各地域にある官民連携プラットフォームを支援するための協定を結ぶ。締結後は専門家を派遣したり財政上の支援措置を紹介したりしてPPP/PFI事業の推進に協力する。協定締結対象を募集しており、3月1日まで受け付け4月上旬に協定を結ぶ。協定期間は2025年3月31日までの1年間。「PPP/PFI地域プラットフォームの協定制度」で協定先の第6次募集を始めた。対象はPPP/PFI事業の推進を目的に、地域単位で地方自治体や金融機関、民間事業者などで構成するプラットフォーム。代表者に都道府県か政令市、人口20万人以上の市区町村のいずれか含まれることが要件。
情報元:建設工業新聞
宇都宮市/産官学の連携母体組織、近く設置へ/共創のまちづくり推進
宇都宮市は産官学のさまざまな主体と連携したまちづくりなどを推進するため、母体となる「PPP/PFI地域プラットフォーム」を近く立ち上げる。2024年度予算案に組織の運営費を計上した。「共創のまちづくり」の推進が狙いの一つ。学識者や各産業の事業者などに参加してもらい、セミナーや勉強会などを開き、課題や情報を共有する。公共施設を整備するに当たって、組織の機能を生かすことも視野に入れている。情報元:建設工業新聞
地下埋設物調査データの活用拡大/無電柱化事業を迅速化/応用地質ら4社
応用地質は21日、日立製作所、NTTインフラネット、アイレック技建との4社で、地中レーダーなどで得られる地下埋設物の調査データ活用市場の拡大検討に関する覚書を交わしたことを明らかにした。無電柱化事業を推進する全国の自治体担当者などに、データ活用の有用性やユースケースを整理・発信して導入・普及を進めることで、より効率的な地下埋設インフラ整備に貢献する。地下埋設物の3次元位置情報を可視化・一元管理する「地中可視化サービス」を提供する日立と応用地質、無電柱化の推進とICTを活用した社会インフラ分野の課題解決に取り組むNTTインフラネット、非破壊探査事業を推進するアイレック技建が連携し、インフラ事業者に寄り添った観点で調査データ活用の高度化と普及促進を図る。
情報元:建設通信新聞
▽2024.2.20
JR西ら/インフラマネジメント事業で自治体支援/30年までに100の実績目指す
JR西日本ら6者は、老朽化が進む社会インフラの維持・更新を支援する事業を共同で始めた。16日付で業務提携。老朽化したインフラの維持や管理を担う地方自治体を支援する。2030年までに100を超える自治体のサポートを目指す。将来は海外での事業も視野に入れる。今後は、事業に応じて各地域の地元企業とも協業する。自治体と契約を結んでインフラサービスを提供するPFIなどの活用を想定。既に20を超える自治体が関心を持っているという。サービス提供に当たり建設会社などとパートナー連携を図り、30年までに100以上の自治体でのサポートを目指す。
情報元:建設工業新聞
自治体の提案受付/ファーム本拠地を募集/千葉ロッテマリーンズ
プロ野球千葉ロッテマリーンズ(千葉市)は、さいたま市にあるファーム(2軍)施設の移転先を公募している。施設と敷地の整備・運営手法について、自治体から提案を受け付ける。パートナー企業などの協力も可能とした。ZOZOマリンスタジアム(千葉市)から車で約1時間程度の場所を想定する。2028年1月からファーム本拠地としての利用を目指す。提案条件として敷地は約11万㎡で、一体的に利用できることを挙げている。自治体が敷地を所有し、20年以上継続して利用できることも求める。施設には野球場(2~3面)、屋内練習場、関連練習施設(ブルペン、サブグラウンド)、クラブハウス、選手寮、駐車場などを設ける。
情報元:建設通信新聞
▽2024.2.16
国交省/スモールコンセッションの推進方策骨子案示す/手続き簡素化で事業の形成促進
国土交通省は地方自治体が所有する遊休不動産の運営を民間に委託し、有効活用につなげる「スモールコンセッション」の推進方策の骨子案を示した。普及啓発を目的とした会議体の設立や事業手続きの簡素化といった具体策を盛り込んだ。3月にも推進方策をまとめ、2024年度から施策を展開していく。自治体や民間事業者、学識者などでつくる「スモールコンセッション推進会議(仮称)」を立ち上げる。事業のノウハウを共有したり、官民のマッチングを促したりして全国的な普及を後押しする。
情報元:建設工業新聞
▽2024.2.15
PPPモニタリング/第三者機関を検討/環境配慮資器材認定工場制度も/下水道協会
日本下水道協会(岡久宏史理事長)は、ウオーターPPPの導入・拡大を見据え、2024年度からPPP/PFI事業の運営管理をモニタリングする第三者機関の在り方に関する検討を始める。環境に配慮した資器材・資器材メーカーに対する認定工場制度適用も検討する。24年度の事業計画に盛り込んだ。13日に開いた事業計画発表の記者会見で岡久理事長は、ウオーターPPPの運営状況をモニタリングする第三者機関について「PPPは官と民がウインウインな形で進めるべきだ。中立的な立場で、公平・公正にモニタリングできる第三者の在り方、権限なども含めて検討が必要だ」とした上で、同協会が第三者機関を担うかどうかについては「決めていない。どういう組織がふさわしいかを考えたい」とした。24年度は、関係団体に課題などをヒアリングし、第三者機関のあるべき姿を検討する。
情報元:建設通信新聞
世田谷区/事業量増大・職員確保困難に対応へ体制見直し
東京都世田谷区は、公共施設や都市基盤の老朽化に伴って今後の事業量増大が見込まれる一方で、年々職員の確保が困難になるという状況に対応するため、2024年度から27年度までの4年間で行政体制の見直しを進める。施設や工事発注の関連では、跡地・空き施設などの有効利用に向けた民間活用制度の構築、道路維持管理業務での包括的管理の導入、土木工事発注での概算数量発注などを検討し、職員が計画検討などの主要業務に注力できる環境をつくる。公共施設整備ではPFIなどの官民連携手法を検討するほか、施設機能の廃止、機能統合・転用などで生じる跡地・空き施設について、売却だけでなく、事業方針の検討段階から民間企業による自由度の高い提案が可能な仕組みとして、方針策定段階から事業者と意見交換する「民間活用制度」を構築する。推進体制として、公共施設マネジメント推進委員会の下に「(仮称)施設利活用検討部会」「(仮称)民間活用検討部会」を設置して新たな仕組みを検討し、25年度からの提案募集を見込む。
情報元:建設通信新聞
▽2024.2.9
内閣府/PPP・PFI行動計画重点分野主要事業の効果紹介
内閣府は、「PPP/PFI推進アクションプラン」で定める重点分野の主要プロジェクトとして24件を公表した。PPP/PFI事業のさらなる普及に向けて、各取り組みの概要や効果をまとめている。公園事業の主要プロジェクトでは「代官山公園官民連携型賑わい拠点創出事業」を取り上げた。公園の整備、管理に民間資金を活用するPark-PFI(公募設置管理制度)の取り組みで、自治体の財政負担の縮減などにつながった。
2023年改定版の同プランでは重点分野に空港、水道、下水道、道路、スポーツ施設などを位置付け、31年度までに重点分野で計575件の事業具体化を目指すとしている。
情報元:建設通信新聞
全国初 みなと緑地PPP/神戸港で計画認定
神戸市は8日、2022年12月の港湾法改正で創設した港湾環境整備計画制度(みなと緑地PPP)を活用した全国初の事例として、神戸港の新港第2突堤で建設している多目的アリーナの運営事業者が申請した計画を認定したと発表した。みなと緑地PPPは、港湾緑地にカフェなどの収益施設を整備し、そこで得た収益を休憩所など公共部分の整備に還元する民間事業者に対して、緑地などの行政財産を長期で貸し付けられる。港湾管理者は緑地の整備や管理にかかる財政負担を軽減できるほか、民間事業者にとっても収益施設と緑地を一体的に整備できるなどのメリットがある。
初弾案件は神戸ウォーターフロントエリアの新港第2突堤内に建設中で、25年4月に開業する神戸アリーナ(仮称)の運営事業者となるOneBrightKOBEが申請した計画を神戸市が認定した。
認定により新港第2突堤の緑地約1.2haを貸し付ける。貸し付け期間は25年4月から55年3月まで。緑地内には2階建て延べ約900㎡の飲食店を整備し、収益は休憩施設の設置、来訪者に対する各種サービスや設備導入、植栽の維持管理や植え替えなどに充てる。
情報元:建設通信新聞
静岡市/2月29日にPPP・PFI地域プラットフォーム、4事業で対話実施
静岡市は29日、本年度第3回PPP/PFI地域プラットフォームを葵区のしずおか焼津信用金庫本店会議室で開催する。市と静岡県島田市が計画している4事業を紹介し、民間事業者と行政が対話する場を設ける。16日まで申し込みを受け付ける。3月1日にはオンライン形式で講演会と報告会を開く。対象事業は▽旧清水西河内小学校ほか学校跡地活用(静岡市)▽用宗Park-PFI事業(同)▽野外活動センター山の家活用事業(島田市)▽神座小学校跡地利活用事業(同)-の4事業。
情報元:建設通信新聞
▽2024.2.5
内閣府/PFI指針6月改正/物価変動に対応
内閣府は、PFI事業の物価変動の影響に対応するため、各種ガイドラインを見直す。事業者や関係団体の要望を踏まえ、物価変動に関する協議を円滑にするための助言などを盛り込む。6月のPFI推進会議で決定する。1月31日に開いた民間資金等活用事業推進委員会事業推進部会で議論を始めた。
PFI事業は長期にわたることから、物価変動が事業者の費用や利益に影響を与えるおそれがある。そのため事業者や関係団体は物価変動の影響を踏まえた既存契約の適切な変更のほか、新規契約についても入札公告日に近い時点での予定価格の見直しなどを求めていた。
これらの要望やPFI事業に関する調査を踏まえ、ガイドラインや基本的考え方などを見直す。会合では改正に向けた検討の方向性を示した。
既存契約の変更では円滑な協議に向けた助言の記載を検討する。入札公告に近い時点の予定価格の見直しは、その積算方法の記載内容を考える。
物価変動に基づくサービス対価の改定については、現行ガイドラインで基準時点を契約締結日が適切としていることから、見直しの必要性や内容を考える。物価変動分の事業者負担に関しては、通常の物価変動は事業者のリスクとし、予測不能な物価変動は管理者と事業者の双方でリスクを分担する考え方を維持する。
情報元:建設通信新聞
▽2024.2.1
内閣府/PFI物価変動対策を検討/新規契約でも予定価に反映へ
内閣府は1月31日に有識者会議を東京都内で開き、PPP/PFI事業を巡る物価変動への対策の検討を開始した。事業者や業界団体の要望を踏まえ、対応を強化。既存契約で必要な契約変更を行うほか、新規契約でも物価変動を予定価格やサービス価格に適切に反映させるよう対策を練る。議論の成果を踏まえ、契約やリスク分担などに関する各種ガイドラインを見直す。新たなガイドラインは6月の決定・公表を予定している。同日に開かれたPFI推進委員会(委員長・北詰恵一関西大学環境都市工学部教授)で検討の方向性を示した。
情報元:建設通信新聞
内閣府/PPP/PFI 分野横断、広域で推進/先行事例の知見展開
内閣府は、自治体の予算や人員の不足を踏まえた効果的なインフラの再構築に向けて、分野横断や広域のPPP/PFIの活用推進に乗り出す。先行事例を類型化した上で合意形成の過程や連携手法などを調査研究し、得られた知見を手引きなどにまとめて横展開していく。1月31日の民間資金等活用事業推進委員会事業推進部会で、取り組みの方向性を示した。
政府の地方制度調査会が2023年12月にまとめた答申では、今後のインフラ老朽化や人手不足の進展を踏まえて自治体の連携を支援するため、国に対して先進事例の収集や取り組みの横展開などを求めた。答申を踏まえ、類似施設の統合や自治体間連携による業務効率化を進めるため、「分野横断型・複数施設型」や「広域型」と位置付けた省庁横断のPPP/PFIの活用を加速する。
情報元:建設通信新聞
内閣府/PPP・PFI事業優良事例表彰制度を創設/初弾は3月29日まで受付
内閣府はPPP/PFI事業に関する先導的で優れた事例を選ぶ「PPP/PFI事業優良事例表彰制度」を創設した。初弾の応募を3月29日まで受け付ける。表彰により、地方自治体や民間事業者の機運醸成を図り、地域でのPPP/PFIを普及したり、事業の活用対象を拡大したい考え。民間事業者の創意工夫の最大化も目指す。表彰式を6月ごろに開く予定だ。内閣府特命担当大臣賞のほか、優秀賞、特別賞を選出する。
情報元:建設工業新聞
埼玉県/17団体がエントリー/スーパーシティプロジェクト合計46市町村に
埼玉県は1月30日、超少子高齢化社会にまちづくりから対応する施策「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」に、新たに17団体がエントリーしたと発表した。このプロジェクトに参加する団体は合計46市町村となり、県5カ年計画における施策指標の2026年度末目標値を前倒しで達成した。引き続き、県内の63市町村すべてへの拡大を目指す。新規団体の取り組みの傾向として、半数以上が▽施設の複合化・拠点化▽公共空間活用によるにぎわい創出▽ウォーカブルなまちづくり▽空き家・空き店舗の活用▽利便性の高いモビリティサービス▽再エネ導入等による災害時電源確保▽電気自動車活用--の7点を挙げた。特に、再エネ導入などによる災害時電源確保は、17団体すべてが取り組む意向を示した。
新規の17自治体は次のとおり。
▽川越市▽川口市▽行田市▽飯能市▽加須市▽鴻巣市▽深谷市▽上尾市▽草加市▽蕨市▽志木市▽新座市▽八潮市▽日高市▽伊奈町▽川島町▽長瀞町。
情報元:建設通信新聞
高松競輪場再整備/余剰地に非日常ホテル/梓・大成らグループ案
高松市は、高松競輪場再整備の公募型プロポーザルで優先交渉権者に特定したチャリロトグループを実施事業者として決定するとともに、提案内容を公表した。サイクルツーリズムのハブとなるホテルを建設し、自転車競技を楽しむ「スポーツゾーン」や高松の魅力あふれる「マーケットゾーン」、多世代が憩える「パークゾーン&チータカ広場」を整備する。再整備の方針は「自転車文化を創造するハイブリッド競輪場」の実現。サイクリストの需要に応え、非日常が体験できるホテルを中心に競輪と市の魅力の相乗効果を生む施設を整備する。スポーツゾーンは、プロとアマ問わずBMX(バイシクル・モトクロス)など都市型スポーツのフィールドとする。マーケットゾーンは、地元と連携して日曜マルシェなどにぎわいの核となる。パークゾーンに隣接させるチータカ広場は、親子で楽しめ、子育て世代が安全・安心に過ごせる地域愛着の場とする。
情報元:建設通信新聞